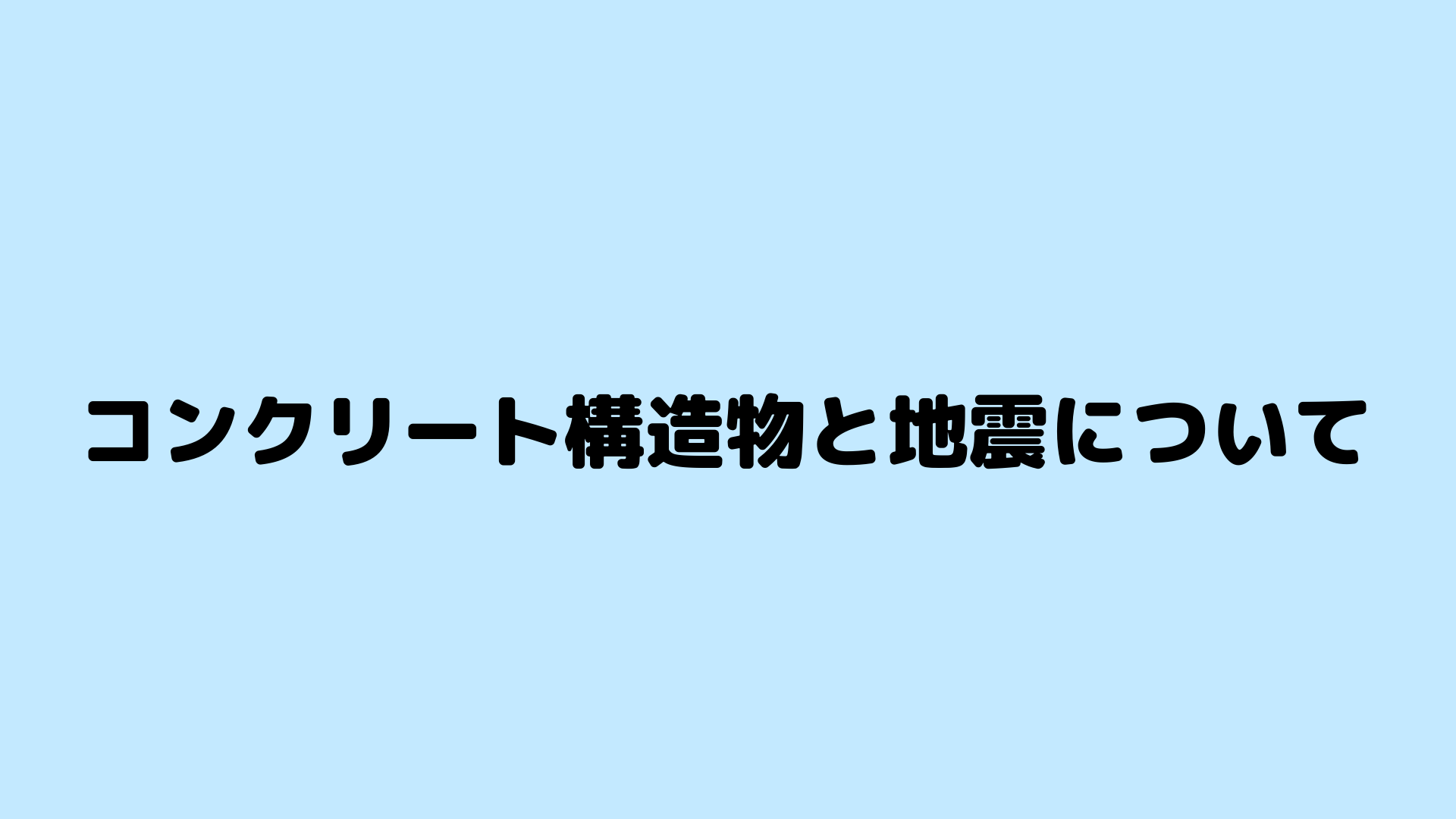こんにちわ。
香川県高松市の㈲生道道路建設です。
日本は世界的に見ても地震の発生が多いです。
一方で、過去に経験した大震災での教訓を生かした結果、日本のコンクリート構造物の安全性は世界でもトップレベルと言えるでしょう。
本記事では、日本で発生した過去の大震災での被災状況や、地震に対する取組みについて説明します。
ぜひ参考にしてください。
コンクリート構造物と地震について
近年の大震災での被災状況
日本では震度6以上の地震が比較的高頻度に発生しています。
また、2011年に発生した東日本大震災の規模は、国内観測史上最大でしたが、コンクリート構造物自体の被害は比較的小さかったと言えるでしょう。
これは、1995年の阪神淡路大震災、2003年の新潟中越沖地震での経験に基づく地震対策に一定の効果があったおかげだと考えられます。
一方、津波による被害は甚大で、橋梁や建築物の崩壊、道路の寸断など、多くの被害が発生しました。
数百年に一度程度の頻度への大地震に対する対策をどうするか?はさらに議論されていくと思われます。
地震に対する指針の変遷
構造物を計画する場合、
・この構造物はどの程度重要なのか
・どれくらいの強度が必要なのか
など、その要求性能のレベルを決める必要があります。
これらの設計手法や基準値を定めたものが各種の設計基準です。
【指針の変遷】
・1931年: コンクリート標準示方書の制定
・1970年: 道路構造令の制定
・1973年: 道路橋示方書として鋼橋とコンクリート橋の基準が統一
・1986年: 許容応力度設計法から限界状態設計法に移行
・1995年の阪神淡路大震災を契機に、コンクリート標準示方書で耐震設計編を制定し耐震性能の照査が導入
大震災に対する取組み
大震災に対してコンクリート構造物に求められる性能は
壊れない事
です。
構造物以外での取組みでは
・セメント系固化材による地盤改良(液状化の防止)
・堤防の基礎部分や道路、既存の基礎部分の補強
などが挙げられます。
以上です。
本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。
お仕事のご依頼はこちらからお気軽にお問合せください。
電話番号: 087-874-6843
FAX: 087-874-6845